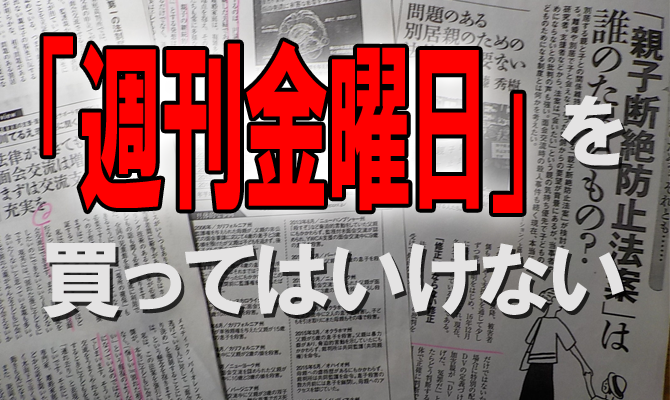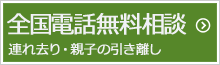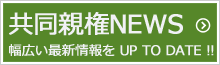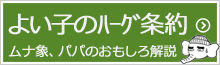宗像 充 「少子化ニッポン」の子育て事情 抜け落ちた視点
『アジェンダ―未来への課題―』22号(2008年秋号)に公表したものです
20号の「アジェンダ」では、「少子化」と呼ばれる日本の子育ての現状と課題が、多様な角度から指摘されている。ところが、すべての論考から欠けていながら無視しえない現実として存在する問題がある。離婚あるいは別居後に、子どもと暮らしていない親(別居親)と子どもとの関係と子育ての現状である。
これまで想定されてきた別居親といえば、妻子を捨てる身勝手な父親の姿であり、あるいは、養育費を払っても子どもの養育には関わろうとすることもない、そういう否定的なイメージしかなかった。したがって、離婚家庭への支援といえば、主に子どもを引き取る側の母子への支援ということしか想定されてこなかった。
しかし、離婚しても子育てにかかわりたいと思いながら、現実は子どもと暮らせないどころか、会うことすらできない親は、今も昔も確実に存在する。さて彼らの存在は、「離婚家庭」ではないのだろうか。
「シングル」に戻る
日本では、未成年の子のいる夫婦の離婚の場合、親権を父母どちらかの親に定め、それを役所に提出することで離婚が成立する。親権を夫婦が争う場合、家庭裁判所に持ち込まれて、調停や審判、あるいは裁判を経て親権を決める。
では、親権を失ってしまった親はどうなるのかといえば、簡単に言えば法的には親ではなくなる。文字通り「シングル」になる。
もしその人が子どもとのかかわりがもともと薄い親であれば、「新しい人生」をやり直すという選択肢もありえるかもしれない。しかし、その人が子育てに積極的に関わっていた場合、親であるのに親であることを否定されること自体、人権侵害にほかならない。いわんや、離婚を契機に子どもと引き離され、まったく子育てにかかわることができなくなれば、それは親としてのその人の人格そのものを否定することである。残念ながら、離婚後にどちらかの親に親権を決めるという単独親権制度が、こういった人権侵害にお墨付きを与える。
法的には親ではないので、親権のない親は、親としての権利義務が解除される。民法には、養育費も子どもとの面会についても何の規定もない。それをいいことに養育費を払わず、親としての責任を放棄する別居親に対しては、養育費の強制徴収という法制度が整えられた。ところが一方で、別居親と子どもとの面会については、何の保障もない。
そもそも離婚そのものがよくないという風潮の中では、離婚したとしても、子どもはどちらかの親が見ればそれでいいし、そのために児童扶養手当もある。単独親権制度を正当化してきた家制度は、こういった「欠損家庭」の存在を家のイレギュラーな形態としてしか扱ってこなかった。いずれにしても家の観点からは、別居親の存在は邪魔なものでしかない。
また同時に、親権のある親にとっても、別居親の存在は悩ましいものである。離婚とはそもそも相手とうまくいかなくなって別れるものであり、普通、別れた後に元夫や元妻とかかわりあいになること自体、当初は激しい葛藤が生じる。
その結果、親権者の面会拒否によって、親子関係が断絶してしまうことは、今も昔も珍しいことではない。
沈黙してきた親子引き離しのサバイバーたち
これまで親子引き離しの当事者たちは、声を上げることがとても難しかった。
根深い差別を再生産する家制度と法制度上の構造とともにそれにはいくつか理由がある。
一つには、親子の引き離し行為が引き離された親の心理に破壊的な影響を与えるからだ。
ぼく自身も引き離しの当事者である。離婚そのものも、双方の親にとってその悲哀の過程を乗り越えるにおいては、相当の時間とエネルギーが必要とされるのだけれど、ぼくの場合、子どもと引き離された後、部屋の掃除や自炊を再開するのに、三ヶ月程度かかった。
愛する子どもと不本意に引き離されることは、心的外傷後ストレス障害(PTSD)や失業、自殺等、さまざまな問題を当事者に引き起こす。子どもと引き離された親の自助グループに参加してみればわかるが、当事者たちは鬱状態に陥って、投薬を受けていたり、通院している人がほとんどである。
また同時に、当事者が自分が置かれた立場をよくわかっていないということがある。多くの場合、子どもと引き離されれば、親権のない親にはなんの権利も保障されていないため、「そういうものだ」と言われれば、それ以上の救済措置はあまり用意されていない。混乱と動揺の中で、自分が一番不幸だと思って、精神的に沈んでいる人も多い。
さらに社会的に声をあげようにも、係争を抱えてそれどころではない。多くの場合、仕事が忙しく、それが離婚の原因になって、出張中に子どもを連れ去られたなどの例もよくあるのだから、いきなり当事者になって孤立し、社会的に発言するノウハウもなければ、運動を始めようにも、余裕も手段もない。
その上、子どもを相手方にとられているという状態で、社会的に発言すれば、それが面会拒否の理由になるのではないかという恐怖が、常に別居親には存在する。
別居親の立場は、たとえ離婚に至らない共同親権の状態においても圧倒的に弱い。
「離婚するまで子どもを会わせない」とか、「慰謝料(解決金)を払うまで子どもと会わせられない」とか、子どもとの面会を取引材料にする人質取引が家裁では日常的に行われている。そして、それを率先して取引材料とするのは弁護士たちである。私たちは、こういった弁護士たちの人権侵害行為を「人質弁護」と呼んでいる。
面会拒否という病理
では実際に子どもと会うことができなくなったとき、会えない親のほうに原因はないのだろうか。その答えは、そうともいえるしそうでないともいえる。婚姻が自由意思において成立するという架空の前提のもとでは、離婚の原因をどちらか一方だけに帰すことは現実問題として難しいが、親どうしの関係と、親子関係を分けて考えることができない親が子どもを引き取った場合、面会拒否という現象は生じる。
なぜなら、現在の法制度のもとでは、子どもと会う会わせないを決めるのは、最終的には子どもを実効支配している親の側になるからである。会わせない理由など、雨が降っても雪が降ってもなんでもいい。
もちろん、子どもとの面会は、判例上も権利として認められているのだが、実際には家裁の調停の現場では、子どもを実効支配している親が強固に子どもとの面会を拒否すれば、具体的に面会を実現するための合意はできない。
また仮に会わせることが決まっても、その内容も、2ヶ月に一度や3ヶ月に一度といったような、どう考えても子どもの利益というよりは、会わせる側の親の都合を優先して決めることになりがちである。
さらに、調停が不調に終わり、審判や裁判に移行すると、裁判所はむしろ面会を制約する決定を出すのが通例である。法律上も、「子どもの福祉」は重視されるが、ところが何が「子どもの福祉」かという共通見解が裁判所にはない。その結果、子どもを見ている側の安定を損なうことが、「子どもの福祉」を害するという、家制度的な発想に強く根ざした決定を裁判所は出しやすく、一方的に泣き寝入りさせられるのは、別居親ということになる。
それに法律上は親権を決めさえすれば離婚は成立するので、裁判所の運用でも親権の帰属を優先して、面会についての取り決めを後回しにすることがある。
子どもを連れ去った親が、離婚すれば子どもを会わせるからと親権を取った上で、実際には子どもとも会わせないという詐欺行為が横行している。この問題において、実効性のある強制力の不在は決定的である。
「ジャングルの掟」
親権のあるなしで子どもとの面会を含めて親としての権利義務が0か一〇〇かになるという事実を知ってしまった親たちは、離婚の過程で壮絶な子どもの奪い合いを展開する。単独親権制度のもう一つの病理である。
子どもを連れ去ったり、DVや児童虐待をでっち上げたり、はたまた人身保護法を目的外利用したり、裁判所でひたすら相手方の悪口を言ったり、相手方との関係を壊す中で子どもの行き先が決まることも多い。親権を失えば、子どもと会うことができなくなるのではないかという恐怖がこういった泥仕合をエスカレートさせ、紛争は長引く。少子化が進み、男女平等が曲がりなりにも唱えられている現在、奪い合いが過熱するのは当然である。
とくに、現在の裁判所の決定は、子どもを先に確保したほうに通常親権を与えるため、文字通りの子どもの連れ去りが横行している。また裁判所もそういった連れ去りを何らとがめるどころか、それを前提にして別居親に子どもをあきらめさせようとすることもある。
こんな現状では、子どもを会わせれば取られると思うから、弁護士たちも調停期間中は子どもを会わせることには消極的である。私たちの会には、子どものことを考えて、調停期間中にも子どもを相手方に会わせていたがために子どもを奪われ、その後一一年間子どもと会えなくなった母親がいる。
会えなくなれば、会えない親は相手への憎悪を募らせる。今年5月、杉並区で子どもの奪い合いになって父親が警官の銃を発砲してしまう事件があり、福島県いわき市では子どもとの面会を求めた母親を父親が自動車をぶつけた末に殺してしまう事件があった。DV防止法による保護命令(接見禁止命令)と子どもとの面会がからむトラブルも珍しいことではない。
DV防止法、ストーカー防止法、人身保護法、児童虐待防止法、それぞれに人権救済の目的を持つ法律だが、不用意に使われたり、その後のフォローアップが用意されていない場合には、親子を引き離すという新たな人権侵害を引き起こしかねない。
実はこういった食うか食われるかの「ジャングルの掟」に対しては、欧米のいわゆる先進国と呼ばれる国々では手が打たれてきた。
日本では母親が子どもを連れて実家に帰るのは珍しいことではないが、欧米では、他方の親の同意のない子どもの連れ去りは犯罪である。また面会拒否は刑法上の犯罪とされる。
そしてこういった法制度は、離婚しても双方の親から養育を受ける権利があるというのが、子どもの利益であるとの共通見解の上に成立している。また同時に、親には子どもを養育する権利があるという当事者たちの訴えが、他国でも同様の問題を抱えていた単独親権制度を、離婚後の共同親権制度へと変えるきっかけとなっていった。
アメリカでは、七〇年代にワラスティンとケリーによる実証研究の中で、離婚した六〇家族の子どもへの継続調査を行ない、両親が離婚した後の子どもと両親との頻繁かつ継続的な接触の重要性、特に父親とよい関係を継続することが子どもの精神的な健康にとって決定的に重要であることを指摘した。このことが八〇年代の共同親権、共同監護の法制化の後ろ盾となった。親子の引き離しは、子どもにも激しい怒りや抑うつ、集中力の欠如に起因する学習遅滞、暴力や非行等の問題行動、さらに子どもが自責の念を抱くなど、さまざまな問題を引き起こす。海外では親子の引き離しは子どもへの虐待とされる。
そして、DVや薬物依存など、親のほうに問題傾向がある場合においても、子どもへの直接的な危険がなければ、そのことで直ちに親の面会権が制約される理由とはならない。
そもそも両親間に葛藤がある場合には、別居親と子どもとの面会は難しいのだが、そのような場合には例えば面会の場所を行政が提供し第三者の監視つきで面会を行う、交通費を支給する、また裁判所や行政が、親どうしの葛藤と親子関係を分けて考える教育プログラムを提供するなど、さまざまな支援体制が充実している。
現在、離婚後の共同親権制度が法制化されていないのは、G7の中では日本だけである。
子どもは親に養育される権利があり、親もまた子どもを養育する権利があるという前提のもと、離婚後の親子関係のルールが日本にも必要とされる。
共同親権を求めて
通常、子育てをするにおいて、親権を意識することはまずない。親権が問題となるのは、一般に親権争いか児童虐待のときだけであり、結局、日本の親権の概念は、親が子どもの権利を侵害するときにもっぱら使われる。親が子どもを支配する「権利」である。
今回、親子の面会を実現する運動を始めてみてつくづく感じるが、現在の単独親権制度という法制度では、子どもの利益を考慮する余地が余りにも狭すぎる。
法的には親ではなく、会うことすら制約される親に、親としての責任や愛情を倫理感だけから求めるのは無理があるし、その結果として、養育費の支払い率も今の制度のもとではこれ以上上がることもないだろう。
そもそも他の先進国では、離婚に際し、養育費と子どもとの面会について定めた養育計画を裁判所に提出しなければ離婚することはできない。また、親権が継続することによって、親としての自覚も促されれば、養育費についての履行率も高まることが予想されるし、実際他の国ではそうなっている。
ぼくたちは、こういった一方の側の離婚家庭の現状を見据えながら、子どもの側から見たもう一つの離婚家庭に対する支援を現在求めている。