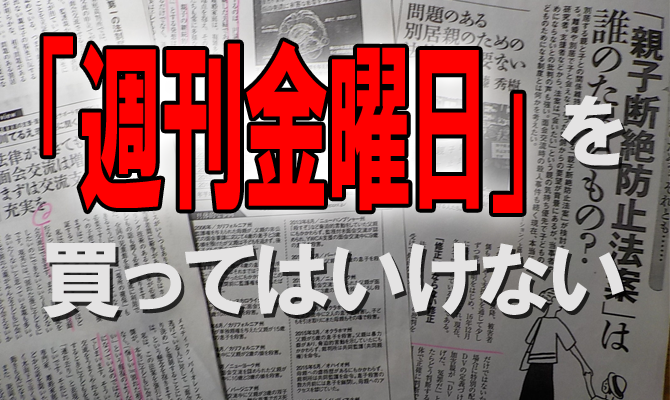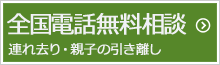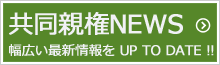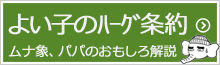宗像 充 「別居親に子どもを育てる権利を」
離婚後・別居後に離れて暮らす親子の交流
雑誌「インパクション」167号(2009年2月15日発行)に公表したものを加筆修正しました。
ぼくはこの1月で自分の子どもと1年3ヶ月にわたって引き離されている父親である。昨年子どもに会えたのは、裁判所でのわずか30分。一昨年、相手方から人身保護請求を申し立てられ、裁判所の決定であっという間に子どもは元連れ合いのもとへと移された。相手方には子どもを宿泊付きで合わせていたので、「拘束」したとの申し立て自体が驚きだった。すぐに子どもは元連れ合いが結婚した相手の養子にされ、面会についての合意も一度しか守られず、しかたなく調停を申し立てた。調停は子どものことは本来関係ないはずの元連れ合いの現夫も対象になり、裁判所での子どもとの面会は、マジックミラー越しにその男性も監視する中で行なわれた。
人身保護当時1歳だった子どもの親権は彼女にあった。話し合いで当時4歳だった彼女の連れ子である上の子どももぼくが暫定的に手元で育てることになったので、彼女の気分が変わり、親権のあるなしで裁判所に申し立てられれば、ぼくには対抗する手段がなかった。現在のところ、ぼくは上の子の面会権も求めて審判を行なっているので、これが認められれば継父の面会権を認める審判例となる。親権のないぼくの現状は、法律にせよ、社会認識にせよ、おそろしいほどに親としての権利の保障がない。
日本の離婚は親権をどちらかに決めることで成立する単独親権制度をとる。親権のない親に、離婚後の親子の面会交流(法律用語で面接交渉)について民法の明文上の規定はなく、結局のところ相手がいやだと言えばそれだけで子どもと会えなくなる。裁判所に調停を申し立てたところで、やはり相手が拒否的であれば、合意に至るのは難しい。子どもに会えもしなくなれば、親として何の実体もないということになる。
これまで別居親といえば、母子を捨て養育費も払うこともない父親というイメージだった。「どうして会えないの」、「よっぽどひどいことしたんじゃない」という別居親への問いかけは、会わせてもらえないからにはそれなりの理由があるはずだという偏見に基づくけれども、実際には、同居親が子どもを囲い込めば、会わせない理由など何でもいい。
離婚後の別居親子の関係は、つまるところ、面会交流と養育費に還元されるのだけれど、このうち、養育費については強制執行などが法的に可能になった。養育とはこれまで金銭的な問題として考えられがちだった。離婚したら子どもは母親が見るのが当たり前、父親は金を払えばいいという発想は、まるで離婚後も性別役割分業が継続するかのような印象を与える。親権といっても通常、親権争いか児童虐待のときにしか聞くことはない。簡単に言えば、親が子どもの権利を侵害するときに主に使われる用語であり、「子どもを支配する権利」がその本質である。ぼくがほしいのは、離れて暮らしていても子どもの成長に親として責任をもってかかわる権利であり、育児への父母双方の参加が政策的にも進められている現在、男女ともにこの要求は高まりこそすれ押さえつけることはできはしない。別居親の存在は、家制度の例外である離婚の中では、母子家庭以上にあってはならないものであり、単独親権制度がこういった階層的な家族関係を肯定する。
親権がなくなれば、子どもへの親としての関わりが持てなくなるというのであれば、「親権争い」は熾烈になる。実際、ぼくが知っているだけでも3件の親権と面会にからむ殺人事件が昨年あった。
調停の開始と同時に、ぼくはこういった現状を社会的に知ってもらう必要を感じ、手始めに自分が住む国立市に面会交流の法制化を求める陳情を提出した。同時に記者会見したこともあり、子どもに会えない親から次から次に問い合わせを受けた。現在7つの自治体が国に法制化を求める意見書を提出している。子どもと引き離されたことによる心理的なダメージは大きく、鬱状態になり投薬を受けていたり、失業したという話も度々聞く。子どもが5年も家に引きこもったままでと、子どもに会えない親の親から相談を受けることも多い。離婚後に相手とかかわりあいを持つことはそもそも難しく、メンタルなサポートも含めて、面会交流への第三者への支援が整えられなければ、双方の親にとっても不安や危険はなくならない。単独親権から双方の親に養育の権利を保障する共同親権に移行した国々では、親子の引き離しは子どもへの虐待と考えられているけれど、国際結婚が昨年過去最高を記録した今日、離婚したら子どもに会えなくなる日本の現状は、強い国際的な非難にさらされている。
現在、ぼくたち別居親は、親子の面会交流を実現する全国ネットワークという別居親の組織を作り、1月20日には議員会館で勉強会を開く。「面会交流を実現する」という名称を付けなければいけないこと自体、いかに「会えない」という現状が知られていないかということの裏返しである。
つまるところ、ぼくたちが求めているのは、「親権」ではなく、「人権」である。