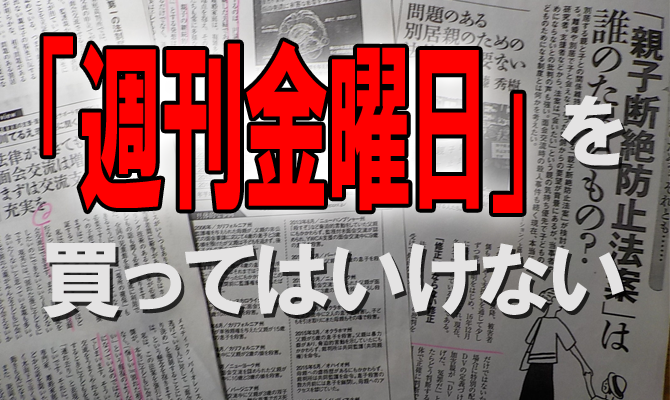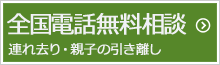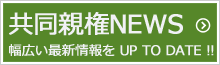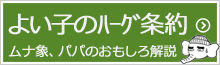面会交流支援の草分けである家庭問題情報センター(FPIC)の機関誌で紹介された、国際的な子の奪い合いについての記事。現状、論点、課題について問題を簡潔かつわかりやすく紹介しています。 夫婦間の子の奪い合いが海外で刑事罰に問われる事件となるのは難しい理屈ではありません。親の同意なく、子どもを住んでいるところから奪って会わせなかったりすれば日本国内でも誘拐です。解放と引き替えに金を親に要求すれば身代金請求にほかなりません。そのような行為が親だからといって許されるはずもなく、従って、海外では実施誘拐罪や面会拒否に対する刑罰が適用されてきました。 国際的な子の奪い合いの防止を目的とするハーグ条約への加盟はこの原則を国内に適用するからにほかなりません。したがって、この論考のように、国内法の改革が必要になります。 もちろん、暴力に関するケースでは緊急避難となりますし、一方の親の同意があったかどうかで、主張が食い違うケースもあるでしょう。したがって、それらは多くのケースで裁判で争点となりますが、国内の法運用の実態は、この点に刑事罰でなされるほどの厳密な証拠調べがなされていないのが実態です。いずれにせよ、子どもの誘拐が認められないのは、万国共通で、日本の文化や伝統の違いがあっても、誘拐を正当化する文化はほこるべき文化ではありません。法制度的な不備は、この点を踏まえてなされるべきです。 原則を踏まえたこのような議論が深まり、広がることを期待します。
【以下】
家庭問題情報誌 ふぁみりお第50号(2010.06.25発行) 海外トピックス50 子どもの幸せのために(3) ―国境を越えた子の奪い合いへの対応― 子どもが不法に奪い去られると子にとってはもとより,奪われた親も蒙るダメージは計り知れません。 とくに幼い子にとっては奪われた状態が長く続くと取り返しがつかなくなる恐れがあるので早急に取り戻すことが必要です。 国際結婚,そしてそれが破綻するケースが増大するにつれ,子が国境を越えて連れ去られるケースが頻発しています。 この場合子を取り戻すには国際的な協力が不可欠なので,これに対応するためにハーグ条約ができました。 本号ではその骨子と運用の状況などを紹介し,併せてわが国の情勢について考えてみたいと思います。ハーグ条約とは ハーグ条約は上記の必要に対応するために,1980年10月,ハーグ国際私法会議で採択され,1983年発効しました。正式には「国際的な子の奪取の民事面に関する条約」と呼ばれます。 日本はハーグ国際私法会議の加盟国でこの条約に署名していますが,まだ批准していないので締約国となっていません。 2010年2月現在,締約国は81か国にのぼりますが,日本はG7(日本,アメリカ,イギリス,フランス,ドイツ,イタリア及びカナダ)の国の中では唯一の非締約国です。 このため諸外国では子を連れて日本に逃げられたらどうにもならないという苛立ちが募っています。 カナダ大使館では,2009年3月日本の法律家や調停委員を集めて勉強会を開き,010年3月各国の代表によるシンポジウムを催しました。 2009年10月及び2010年1月にはアメリカ,イギリスなど8か国の駐日大使から日本政府に加盟を促す申し入れがされました。 逆に日本から子を連れて逃げられた親からも,早くこの条約の適用を受けたいという声が高まり,マスコミでも度々取り上げられるようになりました。 政府は外務省に担当室を設置し検討を始めたということです。条約の基本的な考え方 16歳未満の子を親権・監護権を有する親(又はそれに代わる者)のもとから他方の親や親族などが法によらず,又は親権者・監護者の同意がなく国境を越えて連れ去る, 又は留めおく(以下奪取するという)事態が発生し,親が子の返還を申し立てた場合には,その子を奪取される前に居住していた国に速やかに返還させるというのが基本原則です。 どちらの親が子を引き取り育てるのが,将来にわたって子のためによりよいかという親権・監護権に関する判断を要しないので,速やかに対処できます。 親権・監護権に関する判断は子が居住地に戻された後に慎重にすればよいということになります。 当事者の一方又は双方の国が締約国でない場合には,奪取された親は奪取した親と直接かけあうか,奪取された先の国の機関に自ら又は弁護士に依頼して手続を進めなければなりません。 そのためには多大な手間と費用を要するので,普通の親にはまず不可能でしょう。 裁判に訴えたとしても,その国の法律によって裁かれるので速やかに返してもらえるとは限りません。 この条約の狙いは,奪取があった場合に当事者を救済するとともに,実力で子を奪取してもすぐ連れ戻されるから奪取しても無駄となる, したがって子の奪取の防止に役立つということにあります。さらにこの条約のもう一つの重要な狙いは,国は親子が実際に面会交流できるよう援助する義務を負うことにあります。返還を命じない場合 子が奪取されたら速やかに返還するのが原則といっても,対象は子で成長過程にあり状態は流動的です。親子のあり方や子の心理も微妙で一筋縄ではいきません。 したがって原則にはいくつかの例外が設けられています。 まず,奪取から1年を経過し子が新しい環境になじんでいることが証明された場合には返還を命じることができません。 子を返還すれば心身に重大な危害を及ぼすとか,許しがたい状況に置く重大な危険のあることが証明された場合も同様です。 これは,たとえば返還先で子が虐待を受ける恐れがあるような場合を指しています。その他,申立てをした者が子の移動の時点で監護権を行使していなかった, 移動に同意していた,意見を表明できる程度に成熟している子が異議を述べたなどの場合にも命令は出されません。中央当局(Central Authority)の職務 締約国はこの条約の運用に当たる中央当局を設置することになっています。多くの国では,法務省又は外務省に置いているようです。 締約各国の中央当局は子の速やかな返還の確保その他この条約の目的を実現するために他の国の中央当局と緊密に協力するとともに, 国内で権限を有する諸機関の協力を促進しなければなりません。 子を奪取された親や施設は居住地又はすべての締約国の中央当局に,子の返還を確保するための援助を申し立てることができます。 申立てを受けた中央当局は,子が奪取された先の締約国の中央当局に,その申立てを伝達し手続を委託します。 受託した国の中央当局は他の機関の協力を求めて,子の所在を発見すること,子に対する危害を防止すること,子の任意の返還を実現し又は合意による解決を図ること, 子の安全な返還を確保する措置を執ることなどが義務づけられています。運用の状況 この条約の運用実績に関して,締約国に対して2003年分についてのアンケート調査が行われました。その主な結果は次のとおりです。 返還申立て件数は締約国全体で1259件,対象となった子の数は1784人で,0~4歳が36%,5~9歳が42%で,9歳以下の子どもを対象とするケースが大部分を占めています。 申立てを受けた国(受託国)は,アメリカ23%,イギリス11%,スペイン7%,ドイツ6%,カナダ及びイタリア各4%,以下多くの国に分散しています。 申立てを伝達した国(委託国)はアメリカ13%,イギリス10%,ドイツ9%,メキシコ8%,オーストラリア6%,フランス5%,イタリア及びオランダ各4%などとなっています。 申立て後の主な結果は,任意の返還22%,合意に基づく返還裁判9%,返還を命ずる裁判20%,取下げ15%,返還拒否の裁判13%などとなっています。 返還拒否の主な根拠は,委託国が子の居住地でない15%,申立人に監護権がない8%,奪取から1年を経過している12%,返還すると子に重大な危険が及ぶ恐れがある18%, 子による異議がある9%,などです。わが国の情勢 ハーグ条約を批准してその締約国となるためには,いろいろな準備が必要で簡単でないのは確かです。まず国内法制を整備しなければなりません。 夫婦が離婚しても父母ともに子に責任と権利をもつ共同親権の制度,親子の面会交流を明文化するなどを考慮しなければならないでしょう。 条約の運用に当たる中央当局をどこに置くか,どのような手続で行うか,強制的な手段を執るにはどうするか,といった手続面の整備も必要です。 条約を運用するには人員の配置と予算の配分が欠かせないでしょう。 わが国では親子の一体感が強く,親が子を奪うことは愛情の発露であるとして法に反するという意識が希薄です。 この法意識とハーグ条約の考え方とのギャップが,条約の批准を遅らせる一因になっているのかもしれません。 このギャップを根本的に埋めるためには,国民の親子についての考え方の変革と法意識の向上が求められるでしょう。 ただ,国民の意識は変わりつつあるのに法や制度がそれに追いつかないので不都合が生じるという現象もあるのではないでしょうか。 かつて家庭のことは戸主に任せ,法は立ち入らないことをよしとする家族制度がありました。 戦後家族制度は廃止され,家族の人権が尊重されなければならないという風潮になってきましたが,これを実質的に保障する法や制度の整備はなかなか進みません。 家族制度のもとでは夫婦が離婚すれば妻は家を去り,残された子と会うことは好ましくないとされていましたが, 親子は別れて暮らしても愛情を繋いでいきたいという希望が社会的にも認知され,面会交流が審判例で認められるようになりました。 しかし未だに明文の規定がなく援助態勢も整わないので,家庭裁判所に申立てがあっても解決が極めて困難な事件とされています。 これに限らず家族法の領域では,権利があっても実現の容易ではないことが沢山あります。 たとえば子の養育費が調停で決められても義務者が所在をくらましたり,財産・収入を隠したりすると権利者個人の力で対応するのは困難です。 これもあって養育費の支払いがきちんと履行されるケースは半数に満たないのが実情です。 一般に家庭の問題についてはあまり関わりたがらない,関わるとしても強力な手段を執りたがらない傾向があるようです。 司法機関と行政機関,また省庁間の連携が乏しいことも,その狭間に落ちてしまうケース生み出す原因の一つだと思われます。 しかし家庭の問題,とくに親子やDVなど圧倒的に力が違う者の間の問題については,血縁・地縁共同体が崩れてきている今日, 公の機関が協力して当たらなければければどうにもならないことが多いでしょう。このためには行政機関と司法機関が具体的・組織的に連携するシステムを構築するとともに, 運用に当たっては伝統に囚われない柔軟な考え方をもって積極的で強力に対処することが必要だと思われます。 【「ふぁみりお」50号の記事・その他】