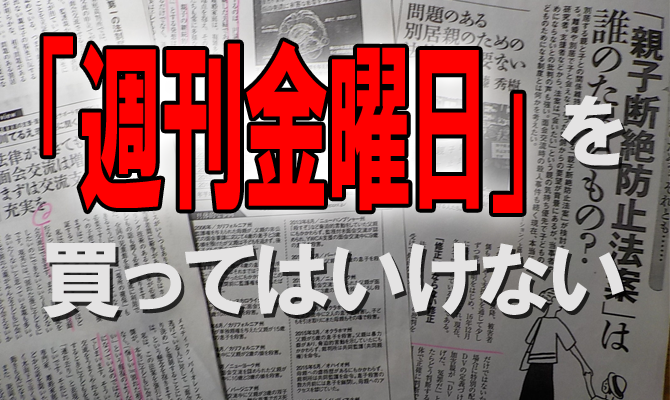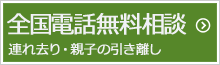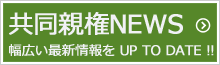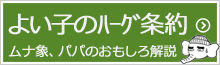本資料は、後藤弁護士の許可を得て公開しています。
弁護士 後藤 富士子
平成■年 離婚等請求事件
原告:妻 / 被告:夫 / 長女
連れ去り:平成■年■月■日
乙31 「離婚後の共同子育て」(コスモス・ライブラリー)
乙32 ビッグイシュー日本版2010.9.15号特集「共同親権」
第2 本件離婚請求は公序良俗に反する
1 「片親疎外」と「単独親権」
被告が長女と面会できたのは、平成20年■月■日に原告が長女を連れ去っ
てから、平成■年■月■日に2時間程度の1回だけである。そして、原告は、
「長女の状態」を理由にして、「年1回」などという全く非常識な提案をした
ものの、最終的には「月1回」程度を原告も受け入れ、平成■年■月■日に調
停が成立した。それにもかかわらず、原告は、1度も履行しないまま、平成■
年■月■日、「当分の間、面接交渉を求めない」旨の調停を申立てた。まさに
「舌の根が乾かないうち」というほど背信的なもので、司法制度に対する挑戦
というほかない。
ところで、調査官報告書や原告の状況報告書を見れば、原告の行為が「片親
疎外」であることは明らかである。そして、このような強固に片親を遠ざける
行為を、棚瀬一代教授は、「心理的な虐待にもあたる」と言う。単独親権者(監
護者)が子どもを一人で抱え込んでしまう「片親疎外」の子どもに与える影響
は、10年後、20年後になって現れることもあるほど、深刻なものである。
「片親疎外症候群(PAS)」という用語を最初に提唱したガードナーは、片親
疎外について「親に対する根拠のない誇張された侮辱や非難にとりつかれた子
どもの障害」と述べ、「親の意識的そして無意識的な要因だけでなく、子ども
自身の要因も片親疎外の悪化に寄与している」とも述べている。
これに対し、他の研究者は、必ずしも親に対する非難に根拠がなく誇張され
ている場合に限られるとは考えていない。ダグラス・ダーナルは「親が子ども
に片親疎外を植え付けるには、実際に起きた立証できる過失を単純に繰り返し
くどくど言えばよい」と述べている。さらに、「片親疎外の標的にされた親に全
く過失がないとは言えない。また、標的親も傷つけられた仕返しをするとき、
疎外親になり得る。そうすると、役割が入れ替わり、今度はもう片方の親が犠
牲者になる。誰が疎外親で誰が標的親か、役割の明確な区別は難しい。たいて
いどちらの親も犠牲者であると感じている。片親疎外はプロセスであり、誰か
のせいにできないことを忘れないのが重要である」という。
ところで、離婚と関係なく、子どもは両親を愛することが大切であり、片親
疎外は子どもに長期的な悪影響を及ぼし、大人になってからの人間関係作りを
難しくする。このことの認識が、日本の家庭裁判所には致命的に欠けている。
米国では、離婚後単独親権制をとっていた1980年までの100年間、別
居親に隔週末の面会交流権が、法律で守られた権利として認められていたが、
共同親権制が導入された後の1984年~85年の時点で、「70%~80%」
の子どもが別居する親と隔週ごとの面会交流を行っている。休暇や特別な日に
おける不規則な交流も含めれば「95%~97%」の高率だという。そして、
裁判所の提示する「相当なる面会交流頻度」は、「隔週末の金曜の夜から日曜
日の夜」「週日に夕食を一度」「主な祝日の半分」「夏季休暇中に数週間を過ご
す」などとされている。
このような事情に照らせば、離婚前の共同親権の法状況にありながら、単に
原告が子どもを連れ去って「身柄を確保している」というだけで、被告の親権
行使が全的に妨げられている状態を、裁判所が容認していること自体、おかし
いのである。日本には「法の支配」はないに等しい。
2 「子どもの視点」から考えよう
アメリカでも、裁判所ではPASの対処法について未だに意見が分かれている
ようである。しかし、多くの裁判官は、疎外されている親と子どもが交流する
時間を速やかに確保できるように指示を出すことに同意している。さらに、片
親疎外が子どもに与える深刻かつ有害な影響を理解させるために、子育てカウ
ンセリングないし親教育プログラムの受講を義務付けることにも大方同意して
いる。また、多くの場合、子どもと両親にはセラピーを受ける指示が出される。
一般的に、裁判所は家族に明確な方向性と枠組みを示す審判を下す。また、指
示に強制力を持たせるため、通常は取り決めの不履行についての制裁措置も定
められる。
そして、子どもが疎外親に強烈に巻き込まれている深刻な事件について、い
くつかの解決策が提案されている。深刻度がまだ低い場合、裁判所の指示が履
行されているかどうかを監視するペアレント・コーディネーターを任命し、裁
判所に報告させるのである(ギャリティとバリス/1994)。深刻度が高い場合に
ついて、ガードナーは、疎外親から親権/監護権を取り上げ、疎外されている
親に変更することを勧めている。
裁判所がいかに効果的な介入をしているか、「ママとその娘」の事例で見てほ
しい。別居前、夫は家族にあまり関与しておらず、夫には離婚後に婚約した女
性がいたというケースである。裁判所は、母親は、①子どもが父親と関わる機
会を意図的に奪ってきた、②子どもが父親に対して自然に抱く愛情や敬意を台
無しにしようと意図的に試みてきた、③娘たちが父親と関わる能力、ひいては
他人と関わる能力全般をひそかに傷つけてきた、④娘たちを自分の感情に巻き
込み、味方につけてきた、ことが明らかであり、その結果、⑤娘たちは母親の
世話をする立場をとるようになり、⑥父親を嫌うと母親が喜んだので(つまり
報酬が得られたので)、娘たちは他人を操作する方法を学んでしまった、と認定
した。その上で、子どもの最善の利益に基づいて、次のような審判を下した。
(1)母親が父親の弁護士の報酬を支払う。
(2)母親が訴訟後見人の報酬を支払う。
(3)審判不履行があった場合の追加費用に備えるため、母親が1万ドルの保
証金を支払う。
(4)母親と父親の両者は、もう片方の親や親戚に対する敬意を持つ。
訴訟後見人の要望として
(5)子どもはセラピーを受ける。
(6)両親はPEACEプログラムを受講する。
このような強力な司法介入は、両親の争いを鎮める効果をもたらしているとい
う。
アメリカの子どもと日本の子どもで、本質的な違いがあるはずがない。親に
ついても同様である。劇的かつ決定的に違うのは、司法であろう。そして、日
本の司法の実態をみれば、アメリカとは全く逆に、疎外親の後押しをし、子ど
もに深刻な悪影響を強固に植え付けている。まさに棚瀬一代教授が警告する
「離婚で壊れる子どもたち」(光文社新書)を裁判所が大量生産しているので
ある。
また、日本では、アメリカでは当たり前の「頻繁な面会交流」は、子どもの
負担になると考えられている。それは「面会」「訪問」(visitation)だからであ
る。「訪問」という考え方は、子どもと親の関係性の価値を低く見積もってい
て、子どもの生活におけるもう片方の親の役割を認めておらず、子どもと「自
分の時間」のために両親が争う火種になっている。むしろ、子どもと過ごす時
間は「子育て時間(parenting time)」というべきである。両親は異なるスタイ
ルを持ち、時間の使い方も違う(両親がそろっている家族と同じように)。し
かし、両親はどちらも親の役割を担い続ける。子どもは家にやってきた「訪問
者」ではなく、そこに住んでいる。子どもには、両親が別々に暮らしていても、
両親との結びつきを感じることが大事なのである。
こうした見地から、原告の対応は父を否定するに等しく、根本的に間違って
いる。
3 「裁判離婚」について
夫婦の合意だけで離婚ができる協議離婚制度がある中で、裁判離婚は片方配
偶者にとって、国家により離婚を強制されるものである。それ故にこそ、裁判
上の離婚原因が限定されているのである。
しかるに、被告には、民法第770条1項1号~4号の離婚原因は存しない。
原告は、同項5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」を離
婚原因として主張している。しかしながら、前述したように、原告が主張する
「婚姻を継続し難い重大な事由」は、客観的事実とはかけ離れた虚構である。
すなわち、原告は、「離婚原因」を捏造して婚姻生活を破壊しようとしている。
このような原告の本件離婚請求が認容されるなら、それこそ家庭裁判所は
「家庭破壊裁判所」になるのであり、「法の支配」は地に落ちる。
また、日本の制度では、離婚時にどちらか一方の親が親権を喪失することに
なっている。婚姻破壊を仕掛け、子を拉致した配偶者が、まんまと離婚と単独
親権を手にすることは、二重に不正義というほかない。しかも、原告は、「離婚
が成立するまで長女と面会させない」というのであり、長女を「人質」にした
卑劣で横暴な対応である。このような「子の最善の利益」を損なう離婚を裁判
所が後押しすることは、あってはならないことである。
(以上)