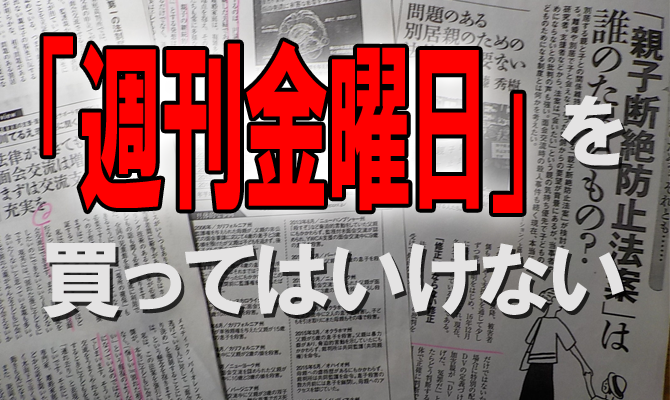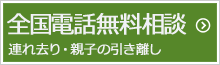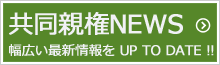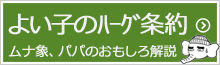弁護士の後藤富士子さんの書き下ろしの論文です。
前半は裁判官のキャリアシステムについて
後半は、国家に対する親の子育て権について触れています。
面会交流の議論をするとき、
親の権利ではなく子どもの権利という意見が散見されますが、
面会交流が離婚と同時に発生する権利なわけではなく、
親の養育の継続という視点からそう呼ぶにすぎません。
子どもは財産と違って分割できないので親の養育時間を配分するわけです。
この論文は、そもそも婚姻中も親の養育権が保障されていない実態を指摘するとともに
現行法制度の矛盾が、新しい制度の方向性を示すことに触れています。
「未来を現在に浸入させる」――体制変革の手法
1 「キャリアシステム」と「法曹一元」
裁判官任用制度として見ると、キャリアシステムは昇進制であるから、「裁判官」といっても身分・給与に等級差があるし、権限にも差がある。統一修習を終了して直ちに任官する「判事補」は、原則として一人で裁判をすることができない(裁判所法27条)とされているから、「独立して職権を行う」と憲法76条3項に規定された「裁判官」に該当するはずがない。
これに対し、「法曹一元」の裁判官は、給源を広く拡大するものの、裁判官=判事は全て同等の権限を有し、身分・給与に等級差もないし、昇進制でもない。実例としては、最高裁判事である。そして、憲法80条1項で下級裁判所の裁判官の「任期は10年」とされていて、終身雇用的なキャリアシステムとは反する原理である。
このように、現行裁判官任用制度は、憲法の価値体系に反するものである。そうなったのは、法曹資格取得後10年の経験を積んだ法曹が任官するというのでは、必要な数の裁判官を確保できないという事情による。それが、「判事補」という、キャリアシステムを温存する「がん細胞」みたいなものを生み出した。
ところで、弁護士として裁判実務に携わっていると、担当裁判官の資質・能力に極端な差があり、全く不公平である。「あたり~」「はずれ~」と依頼者に説明し、「はずれ裁判官」に判決や審判をさせないように苦労している。全体的にどうしょうもなく質が低下しているが、それでも「聞く耳」をもつ裁判官ならなんとかなる。翻って、身分・権限・報酬に差があるくらいだから、裁判官としての資質・能力に差があるのも当然なのに、あたかも「どの裁判官でも品質は同じです」と利用者を欺いている。
このような、利用者にとって、それ自体「不正義」な裁判官任用制度を維持したら、司法は崩壊する。司法が崩壊すれば、「法の支配」は無に帰し、日本社会は無法地帯と化すのである。実際、その兆候は顕著になっている。そうすると、キャリアシステムは変革されなければならないが、どのような制度にするかといえば「法曹一元」であろう。
「法曹一元」制は、現行裁判所法に原理が埋め込まれている。法曹人口が増えれば、必要な数の裁判官を確保することも可能になる。そして、「一元判事」は、最高裁判事として現に存在している。したがって、裁判官任用制度の体制変革はリアリティを強めている。それにもかかわらず、日弁連は、旧体制である「給費制統一修習」にしがみつく。これを守旧派といわずして何というのか。「市民のための司法改革」だなんて、冗談はよしてほしい。
2 核家族の自治――国家に対する親の「子育て権」の確立
現行民法で離婚後は単独親権とされているのを、離婚後も共同親権に法改正しようと提言して15年以上経つ。ところが、「離婚後の共同親権」どころか、「離婚前の単独親権前倒し」が家裁実務で横行している。どうして、こんなことになるのか? その原因は、国家との関係で「親権」を親の自然的権利と認めないからである。
ドイツ基本法6条2項は「子の養育および教育は両親の自然的権利であり、かつ、第一次的にかれらに課せられる義務である。国家は、両親の活動を監督する」と規定しているが、これはワイマール憲法に由来する。すなわち、ドイツでは、第二次大戦以前に既に「家族」は「血族共同体」ではなく、「夫婦と子ども」という核家族であった。そして、この規定の意味は、まず親の自然的権利として国家に対する「責任領域」が設定され、義務の不履行があれば、国家がその領域を縮減して介入するシステムを予定する。したがって、両親の離婚について単独親権とされるのは、国家が親の責任領域を縮減して介入し、「子の福祉」の見地から単独親権者を指定するのである。離婚後も共同親権制になったのは、「子の最善の利益」についての科学的知見に基づく社会的認識の変化による。つまり、国の公共政策が変化したのである。
これに対し、日本の戦前の「家制度」は、まさに血族共同体であり、国家に対し責任領域を形成していたのは「家長」である。つまり、日本国憲法により「家制度」が解体されたとき、「家長」に代わる者として「国」がしゃしゃり出てきただけで、「家族の自治」は「家制度」の解体とともに消滅した。換言すると、日本の「親」は、国家との関係で、「子育て」について自然的権利と認められたことはないのである。
したがって、離婚成立前の共同親権の法状態で、国家により片親の親権が剥奪される事態を許していては、離婚後の共同親権どころではない。「両親の自然的権利」を法的に承認させることこそ、現在の焦点である。そうすれば、「子の最善の利益」についての世界共通の理念に照らし、日本でも離婚後も共同親権になるはずである。
3 体制変革のレーニン的手法
「キャリアシステム」と「法曹一元」。「単独親権」と「共同親権」。
「現行制度」と「新しい制度」。これを二元的に捉えていたのでは、どこまでいっても両者は不連続であるから、新制度を実現することは不可能である。
しかし、レーニンのように、一元的に捉えれば、必ず両者は連続する。すなわち、現行制度の矛盾を克服するものとして新制度が構想されるのだから、現行制度の中に新制度は胚胎しているのである。「未来を現在に浸入させる」というのは、制度変革の手法なのである。
【参考文献】白井聡「未完のレーニン」(講談社選書メチエ)
(2010.8.5 後藤富士子)