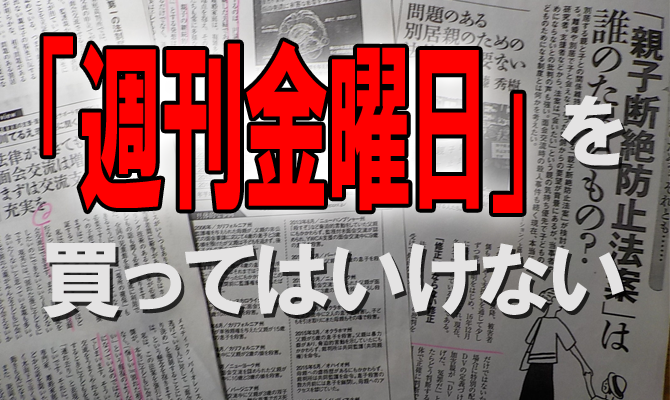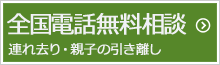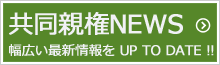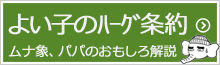本資料は、後藤弁護士の許可を得て公開しています。
控訴人:夫 / 被控訴人:妻
長女 / 長男 /連れ去り:平成■年■月下旬
控訴人訴訟代理人弁護士後 藤 富 士 子
第3 「子育てする親の権利」と「子の最善の利益」
1 「子どもの権利条約」とドイツの法改正
ドイツ民法の親権法制は、日本の現行民法と同じものであったが、1979
年の法改正によって、「親権」という用語は「親の配慮」という用語に変更さ
れ、さらに、1997年の改正により「両親は、未成年の子を配慮する義務を
負い、かつ権利を有する。親の配慮は、子の身上のための配慮と子の財産のた
めの配慮を含む」という現行法になった。この規定の意味は、①両親による共
同性、②全体性、③義務性、④第三者に対する絶対性、⑤人格性、⑥監督性、
⑦理念性、⑧名誉性、⑨実用性、⑩社会的親の権限強化、⑪漸進性、であると
いう。①は、父母間に婚姻関係がなくても共同配慮であり、日本の民法(常に
単独親権)と対照的である。④については、親の配慮は子との関係では義務性
をもつが、第三者に対しては親の配慮権は絶対的効力を有する。⑤は、親の配
慮は、最高の人格的権利で、この権利は放棄できない。この性格ゆえに、別居
・離婚後の単独配慮や養子縁組の同意など親の配慮を自ら手放すときに親同士
の同意では足りず、裁判所の司法判断を要する。
ところで、「親の配慮」が別居や離婚でどのようになるかという点で重要な
のは、「単独親権制」とのかかわりである。1976年の法改正前は、父母間
で親権の帰属について意見が一致しないときに、裁判所が決める基準として、
「子の福祉」と並んで、婚姻破綻についての有責性を親権の単独帰属の判断基
準としてあげていた。ところが、同法改正によって、離婚法で完全破綻主義が
採用されるに至り、婚姻破綻の有責性を親権者の決定基準にできないことにな
り、裁判所は「すべての事情を顧慮して子の福祉に最も良く合致する取決めを
行う」とされた。これに連動して、家庭裁判所制度を導入した。その目的は、
①専門裁判官としての家庭裁判官制度を設け、専門教育を受けること、②婚姻
事件および関連事件を同一家庭裁判官に集中すること、③離婚事件の一回的解
決の要請から、附帯処分も同時に弁論を行い、同時に裁判することである。こ
のために生み出された制度が「手続の結合」である。概略、日本の現行制度に
似ている。
ところが、1982年11月3日、連邦憲法裁判所は、離婚後の親の単独配
慮規定は、基本法第6条2項1文(子の養育および教育は、両親の自然の権利
であり、かつ、何よりもまず両親に課せられている義務である。その実行に対
しては、国家共同社会がこれを監視する)に抵触し、無効であるとする違憲判
決を下した。それは、父母が共同配慮に合意する場合でも必ず単独でなければ
ならないとすることが違憲であり、共同配慮は例外的なものだと考えていた。
つまり、原則共同配慮というのではなく、共同配慮が可能になったということ
である。このような経過を経て、1997年の現行法への改正がされた。
この改正の目的として挙げられているのは、①子の権利の改善・子の福祉の
促進、②子の福祉に合致する限りでの親の法的地位の強化、とりわけ不必要な
国家の干渉からの保護、③嫡出子と非嫡出子の法的差別の撤廃、④不必要な重
複や二重規定を回避して簡明化を図ることとされている。ここで注目されるの
は、1979年法に大きな影響を及ぼした「主たる養育者の重視(事実上母が
多かった)」理論と並んで、他方の親の重視、夫婦は離婚しても子にとって父母
であるということに変わりはないという考え方が重視されるようになったので
ある。この結果、父母間の親の配慮をめぐる争いが激化して長期化すると危惧
された離婚手続と親の配慮の帰属決定の強制結合は廃止され、父母が離婚後も
共同配慮を継続するということで合意している限り、裁判所はその合意に干渉
しないという共同配慮を原則とする改正が行われたのである。
なお、この改正は、子どもの権利条約によってもたらされたということであ
る。それ故、旧態依然の日本民法を説明したとき、「日本は子どもの権利条約を
批准していないのですね?」という質問がされるという。日本も、国連採択か
ら5年遅れて1994年に批准・発効している。
2 「人間らしく育てる」には―8歳までに「普通の環境」に置くこと
被控訴人は、ドイツ法における「親子の交流と子の意思」をめぐる佐々木健
論文を援用して、「PAS」理論を司法的判断に組み込むことが否定されていると
している。しかしながら、まず指摘したいのは、ドイツでは既に共同配慮の法
改正がなされており、父母間で合意があれば裁判所は干渉しないから、実質的
に争いになるのは父母間で共同配慮の合意がない場合であるが、その場合、「子
の意思」だけで結論が出る訳ではない。そして、佐々木氏は、「ドイツ親子法に
おける子の意思の尊重―家事事件における子の意見聴取と手続保護人」「手続保
護人の実務の現状と課題―ミュンヘン子どもの弁護人協会の活動への現地調査
から」を先行論文として発表している。これらを読むと、日本の法制度がいか
に遅れているか、「子どもの権利条約」が活かされていないかを痛感させられる
だけでなく、家裁裁判官や家裁調査官の専門性への疑問、「報酬目当ての私的実
業家」のような弁護士、当事者の長い人生を展望した上での解決が図られない
こと、等々、悲観的になるばかりである。そして、被控訴人代理人が、「PAS」
が批判されているからというだけで、自らの主張の証拠とする態度こそ、今の
家裁の病理だと思わせられる。なお、佐々木論文での「PAS」の引用について、
いずれ反論の論文が発表されるであろう。
ところで、被控訴人は、離婚訴訟における調査官報告書を証拠にして、「監
護に問題がない」と主張する。しかしながら、調査報告書を読む限り、たいて
いの常識ある人は、「子の監護の現状に、特段の問題は認められない。」と結
論することはないと思われる。調査報告書によれば、長女も長男も、学校や
保育園で、母である被控訴人以外の親族の話をしていないが、それは、専ら
母子3人での閉鎖的生活をしているからで、実態を反映している。
しかし、脳科学の見地からすると、このような養育環境は、子の健全な発達
・成長にとって極めてリスキーとされている。澤口俊之『幼児教育と脳』(文
春新書)から、関連する要旨を引用する。
アメリカの著名な認知心理学者ハワード・ガードナーは、「われわれの知性は一つで
はなく、多数の並列した知性からなっている」という多重知性理論を提唱した。つまり、
知性は一つではなく、複数の知性が多重しており、その各々の知性はある程度独立して
働くことができるという考えである。彼の分類は6つの知性であったが、最新の認知脳
科学の成果を取り入れると、人類の知性は大きく8つに分類できる。言語的知性、絵画
的知性、空間的知性、論理数学的知性、音楽的知性、身体運動的知性、社会的知性およ
び感情的知性の8つである。さらに、これら8つの知性を総括しコントロールする知性、
いわば「超知性」としての「自我」がある。「自我」は、自分のもつ多重知性を総括し
てうまく操作し、将来へ向けた計画を立てつつ前向きに生きる知性であり、多重知性の
統括者、「スーパーバイザー」として、最も高度な働きを担い、人格(性格)、理性、さ
らには主体性、独創性・創造性などにもこの知性が中心的な役割を持つ(17~19頁)。
人間らしく育てる、幸せになるように育てる-このことこそが幼児脳教育の根幹にな
るべきとすれば、脳科学や進化生態学の観点から「前頭連合野を育てる」という解答が
ごく簡単に導き出される。前頭連合野は「ヒトを人間たらしめる脳領域」であり、前頭
連合野の働きが「人間らしさ」をつくる。前頭連合野の中心的な働きは「自我」である
から、「人間らしさ」とは、「自分自身のもつ多数のフレームの能力を把握し、うまく操
り、将来へ向けた計画を立て、前向きに努力すること」としての自我フレームの本質的
な働きのことである(159~167頁)。
自我と社会的知性、そして感情的知性はそれぞれ前頭連合野の別の領域によって主に
担われているが、前頭連合野を広くみた場合、これらの知性は前頭連合野が担う中心的
な知性群だといってよい。そこで、これらの知性群を前頭連合野(前頭前野)の知性、
すなわち「前頭前知性、PQ(Prefrontal Quotient)」と総称する。PQは進化的な要因
に強く駆動されて発達してきたものであり、基底となる目的は「社会の中でうまく生き
て、最愛の配偶者を得て子どもをつくり、きちんとした成人として育てること」である。
人間の脳の大きな特徴は、発達した前頭連合野とその働き-自我を中心とした社会的知
性と感情的知性の複合体、PQ-であり、PQこそが「人間らしさ」をつくる。したが
って、PQフレーム(自我フレーム+社会的知性フレーム+感情的知性フレーム)を発
達させることこそが、幼児脳教育の根幹になる(172~173頁)。
PQを育むための環境は「普通の環境」-「豊かな社会関係にさらされる」という環
境である。つまり、子どもどうし、兄弟姉妹どうし、おじおばとの、そして近隣の人た
ちとの関係。そして両親からの父性(社会のルールと規範、さらには価値観・倫理観を
子どもたちの脳に刻み付ける点において父親の役割は大きい)と母性(ヒトの赤ん坊は
「未熟児」として生まれるので、その未熟児を育てるために、幸福感の源ともなるセロ
トニン系が「母性愛」の基礎としてある)をベースにした多様な関係。そうした環境が
PQ発達のために重要な「普通の環境」である。これに対し「普通ではない環境」をロ
ジカルにいえば、「孤独に、かつ、父親からのきちんとした影響・指導も母親からの豊
かな愛情も受けずに育つ環境」である(188~206頁)。
PQフレームにとって、幼少期での「普通の環境」は決定的に重要である。人類の場
合、0歳から8歳くらいまでの間に「普通の環境」において育てなければPQフレーム
は十分に発達しない。そして、深刻な影響が(脳内物質への影響を含めて)生涯にわた
って及び続けるのである。PQは人間の根幹をなす知性である。このフレームを豊かに
育むことなくして、子どもたちは人間らしく成長し幸福感や達成感をもって生きること
は適わない。幼少期に是非とも「普通の環境」にさらさねばならないのである(196頁)。
以上の脳科学の知見を得ると、これ以上、長女・長男を異常な監護状況に
置くことは許されないと思われる。
3 「子の最善の利益」のために被控訴人がなすべきこと
被控訴人は、単に控訴人と離婚できればよかった訳ではない。「DV被害者」
を装って、子どもらの親権者となって、離婚後の生活保障を得ようとしたもの
であろう。換言すると、被控訴人は、子どもたちを自らの生活手段として利用
しているというほかない。
被控訴人は、「子の最善の利益」のために、控訴人ら親族との交流を速やか
に実施すべきである。
日弁連法務研究財団『子どもの福祉と共同親権
―別居・離婚に伴う親権・監護権法制の比較法研究』
鈴木博人論文 129~152頁
(以 上)